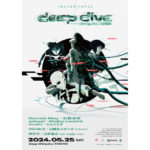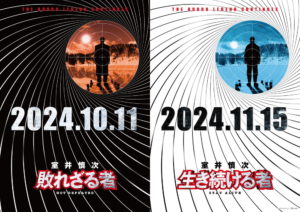|
第1回新潟国際アニメーション映画祭開催へ2023年3月、第1回新潟国際アニメーション映画祭を開催することが決定! 東京会場では本映画祭の審査委員長に就任、日本が誇る映画監督・押井守と、フェスティバル・ディレクターとして、40年近くの歴史を持つアニメ情報誌月刊「Newtype」の元編集長にして現KADOKAWA上級顧問の井上伸一郎、東京の映画祭事務局長として、大ヒット作『この世界の片隅に』、『機動警察パトレイバー』のプロデューサーであり、プロデュース会社ジェンコ代表の真木太郎が登壇。カンヌ会場では、本映画祭のプログラミング・ディレクターとして国内外のアニメーションに精通するジャーナリスト数土直志が、更に本映画祭の本拠地となる新潟の会場では『スモーク』や最近作『アネット』など数々の国際共同製作作品のプロデューサーとして知られる配給会社ユーロスペース代表にして映画祭実行委員会代表の堀越謙三、新潟の映画祭事務局代表として、映画監督のナシモトタオが本記者会見に臨みました。 第1回 新潟国際アニメーション映画祭」記者会見日程:5月23日(月) オンライン中継参加<カンヌ国際映画祭会場>会場:ジャパンパビリオン(インターナショナルビレッジ 116) |
 |
記者会見まず、フェスティバル・ディレクターを務める井上伸一郎による本映画祭の概要と方針説明からスタート。 そして、本映画祭では単純にアニメーション映画を上映するだけではなく「アニメやコミックの研究論文を発表していく、そういうプログラムを作っていく」ことにも言及、「未だ世界中で黒澤明や小津安二郎の映画が観られているのは、海外の日本映画研究家が海外で作品を発表しているから」であり、しかし「残念ながら日本人の研究は、海外であまり発信ができない状態となっています。日本のアニメやコミックの研究論文や書籍等を本映画祭から発信し、アニメの地位向上に繋げたいと思っています」とも述べ、最後「日本のアニメは、昨今の全世界レベルの配信網によってグローバルコンテンツとして進化しました。この進化を更に進めることが重要です。そしてよりクリエイティブな側面からの研究によって、より深く作品を理解することで産業価値を上げていきたいと考えています」とその想いを伝えた。 審査委員長を務める押井守からは「映画祭にとってコンペは、一番求心力のある大きなイベントだと思っています。これまでアニメーションのコンテストは、たくさんありましたが、例えばアヌシー(国際アニメーション映画祭)とか、有名な広島(国際アニメーションフェスティバル)などは、基本的にはアート系の作品のアニメーションのコンテストだったと思います。(本映画祭の特徴は)商業作品に特化し、エンターテイメント作品のコンペにしていることだと思います」と説明、その上で「今までそういったコンテストは確かに聞いたことが無いし、なぜ無かったか?というのはいろいろ理由があると思うのですが、一つには僕らのアニメ業界というのが、人の作品の評価をしない、という特殊な世界だったんです。それが最大の理由かなと僕は思っています。しかしそれは悪しき伝統で、今回はそういったものをぶち破る契機になればいいな、と思っている」と同時に「出品する人たちにどんなメリットを作ってあげられるのか考えなければなりません」と映画祭としての役割も提示、「『何をやっても許されるのか、許されないのか』どちらにせよ、審査委員長が決めたことだから、ということになるのかもしれない」「僕の方針としては審査委員長を引き受けた以上は、自分のポリシーで作品を選びたいと思っています。作品の規模であるとか、興行成績であるとか、作った会社の規模であるとか、監督の評判であるとか、そういったことは全部無視して本当にクリエイティブで情熱が感じられる作品を選びたいと思っています」と述べた。 更に、「アニメーションという文化は、確かに真ん中に作品がある」「周辺に様々な文化が集まってること」も魅力だと述べ、そのため、本映画祭に期待することとして「例えば、声優さんの人気だったりとか、コスプレイヤーであったりだとか、ゲームであったりとか、たくさんあるわけでそういったものが全体として盛り上がって、楽しいお祭りになればいいんじゃないかと」「業界の人間とか、日本のアニメファンが集まった楽しいイベントになれば最高だと思ってます」そして「あとは業界の人間にとっては6日間の期間があるわけです。普段なかなか観る機会の無い作品をまとめて観るチャンスだったりしますし、普段会うことがない監督同士が会ったりして、そういった交流の場になれば最高だなと思います。昼間のコンペが終わった後に、語り明かす、悪口言うとかね(笑)。意義のあるイベントになってくれればと思っています」と期待を込めた。 続いて、カンヌの会見場にいるプログラムディレクターの数土直志より、プログラムの内容及びセレクションの方針を説明。<アニメーションの楽しさをもっと多くの人に知ってもらいたい。アニメーションの新たな意味づけをしたい>との想いとともに新潟国際アニメーション映画祭がスタートすること、そして、現在のアニメーション文化の多様性の最先端である<長編アニメーション>を重視することで「ヨーロッパの巨匠たち、巨大な予算をかけるハリウッド製作のCG、“アニメ”と呼ばれる日本の2Dスタイル、さらに多くの地域から独自の文化と歴史を背負った作品」に共通の視点を与えることで、分断を超えた新しい価値づけ、そこに作品の並列化を生み出したいこと、様々な作品を手軽に観られる時代になったからこそ、映画祭を通して<アニメーションを観る体験>を提供したいことなどが語られました(※宣言全文は別途資料添付)。 最後は新潟の会場より「なぜ新潟で開催されるのか?」ということについて、本映画祭の実行委員会代表である堀越謙三より説明。「新潟では約30年の間に3000人のアニメ、マンガのクリエーターが育成されている。人材育成では日本で最も刺激があり、なおかつ大学にはアニメ・マンガ学部がある。これはアニメーションの技術者だけではなくて、プロデューサー等も含めた、アニメーション業界が必要とする人材を全て新潟で、しかも制作現場で育成できる、ということは強調しておきたい」「また新潟は、ロシア、朝鮮半島、中国に向かった日本海最大の国際貿易都市として、300年以上の歴史を持つ。それはイタリアのジェノヴァやヴェネツィアなどの地中海に向いた海洋都市、あるいはドイツのンハンブルクなど、北海に向いたハンザ都市などの自由都市と同様に、新潟は、市民が自分たちで統治してきた市民都市としての歴史がある」ことが非常に特徴的であり「批評精神、自由な想像力が培われて来た。その土壌こそ新潟が多くの著名なマンガ家やアニメーション・クリエーターを輩出してきた理由であり、この映画祭をやる理由だと言えます」と述べ、また「新潟は海外貿易ばかりでなく、映画祭のロゴに採用した北前船で北海道から京都へと最高の食材を運び、日本食の味の基本を決めた港でもあります。新潟は日本で一番お酒のおいしい所、飲んだり海の幸を食べたりしながら楽しくアニメーションを語れる場所を提供して、新潟で映画祭を開催するもう一つの理由にしたい」と語りました。 |
 |
質疑応答のダイジェストQ:スペインのジャーナリスト(@カンヌ) A:プログラミング・ディレクター:数土直志 Q:東京のジャーナリスト A:新潟国際アニメーション映画祭事務局長(東京):真木太郎 A:審査委員長:押井守 Q:フランスのジャーナリスト(@カンヌ) A:プログラミング・ディレクター:数土直志 |
 |
【第1回新潟国際アニメーション映画祭】長編商業アニメーションにスポットを当てた、長編アニメーション映画のコンペティション部門をもつアジア最大の祭典として、新潟から世界へアニメーション文化を発信していく映画祭。 英語表記:Niigata International Animation Film Festival
|
 EIGAJOHO.COM
EIGAJOHO.COM