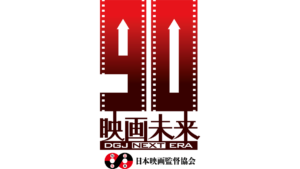|
授賞式レポート今年で5回目を迎える東京ドキュメンタリー映画祭(12月23(金)まで新宿K′s cinemaにて開催中)の授賞式が、折り返しの12月16日に開催された。受賞作品などコンペティション入選作品は、12月17日(土)より2回目の上映があり、大阪のシアターセブンでは、反響の大きかった作品を中心に、東京ドキュメンタリー映画祭 in OSAKAが2月25日(土)〜3月3日(金)に上映となります。 現代社会ならではの生きづらさや先の戦争の傷あと、地域の暮らしや家族との葛藤などを粘り強く見つめた、作り手の真摯な姿勢が目立つ今年のプログラム。「長編」「短編」「人類学・民俗映像」の各コンペティション部門のグランプリ、観客賞が発表されました。 受賞作品一覧■長編コンペティション部門グランプリ: ■短編コンペティション部門グランプリ: ■人類学・民俗映像部門グランプリ(宮本馨太郎賞): |
 |
冒頭、顧問の矢田部吉彦が登壇。 「ドキュメンタリー映画の果たす役割はますます大きくなっている。個人の物語を深く掘り下げて、世界に発信していくという形で作品が作られているのが心強い。本映画祭は、限られた予算の中、世界と関わりのある作品も多く集めている。民俗学と関わりの深い映像作品を特集するという独自の切り口を展開して、個性のある映画祭に成長している」と挨拶した。 ■長編コンペティション部門 長編コンペティション部門の審査員の伊勢真一(映画監督)は、審査の基準について、「完成度というか、作品がどういう形でできて、観る人にちゃんと届けようという意思があるか」と説明。 審査員の鈴木一誌(ブックデザイナー)は、グランプリを受賞した『アダミアニ 祈りの谷』について、「ジョージア、チェチェン、コーカサス、キスト人、パンキシ渓谷など、全く知らない場所について教えてくれたのと、普通の人の生活を淡々と描いて、物語に引っ張らなかった」と評価した。 受賞した竹岡寛俊監督は、「僕が何かをしたというよりも、映画に出てくれた方々の個々の物語が強くて、最後まで離れずに僕に見せてくれた」と出演者に感謝を示した。 準グランプリの『霧が晴れるとき』について審査員の伊勢真一は、「しっかりした取材力と、映像がちゃんとあった」と評価。 本作プロデューサーの平野晃弘は、「企画から10年の歳月をかけて完成した」と苦労を吐露した。 観客賞を受賞した『Paper City/ペーパー・シティ』の植山英美プロデューサーは、エイドリアン・フランシス監督からの、「ジャパンプレミアの場所を探していたところ、このような素晴らしい映画祭で初めて上映することができて、心から喜んでおります」というメッセージを代読した。 ■短編コンペティション部門短編コンペティション部門について、審査員の舩橋淳(映画監督)は、「自分が生きている社会や歴史、コミュニティの中で、薄々感じているがはっきりと認識はできていないある問題やある美しさに向けてカメラを構え、変わりゆく社会や変容していく人々の姿の中に時代が映り込んでいたり、そんな時代と日常を映し出す鏡としてドキュメンタリーを撮っている作家の飽くなき好奇心を露呈している作品を高く評価したい」と評価基準を発表。 グランプリの『火曜日のジェームズ』について舩橋は、「病気で死にゆく母親と主人公の関係が、ユーモアに満ちたAIとナレーションの間に悲しみが滲むように浮き出てくる。コロナ禍のネット空間からはみ出してしまう人間性がドキュメントされていた、知的でヒューマンな作品」と評価した。 本作コーディネーターの林里穂は、「監督のディーター(・デズワルデ)とは、マッチハットという、パッションプロジェクトに協力者が必要な人を結ぶプラットフォームで出会った。彼の映画を見て心が動き、ぜひ本映画祭に応募したいと思って応募し、この結果で嬉しい」と嬉しそうに話した。 準グランプリの『待ちのぞむ』について、舩橋は、「『ビランガナ』と呼ばれるバングラデッシュの強姦被害者と日本軍によるコリアの従軍慰安婦、二つの国での性暴力被害者を横断するように描き、人生を奪われてしまった女性たち、当事者の痛みを照射し、日本・パキスタンによる性暴力への被害を糾弾した。作り手の国境を超越して問題を炙り出す視点の高さを高く評価する」と受賞理由を説明した。 審査員の渡辺勝之(JapanDocs主宰)からは、「あくまで今回の審査員である2人で選んだ受賞作。ドキュメンタリーの見方や思いや評価の絶対的な尺度はない。作った作品を置いておくだけでなく、劇場やネットでできるだけ多くの人に見てもらえるような取り組みをしていただければ」と叱咤激励があった。 ■人類学・民俗映像部門人類学・民俗映像部門の審査員の市岡康子(映像ディレクター)は、「7作品、スケールといい、題材の広がりといい、バラエティがあって、どれが優秀というのを決めるのは難しかった。受賞作品以外の作品もそれぞれ魅力があり、かなり悩んだ。」と、映像作家ならではの審査員としての悩みを吐露。 グランプリ(宮本馨太郎賞)の『ウムイ「芸能の村」』については、審査員の北村皆雄(ドキュメンタリー映画監督)が、「(本作は、)沖縄の宜野座村という一つの町で、それぞれ生活者でありながら、芸能をやっている多くの人たちの生活と芸能を捉えたもの。地域と村の人々、先祖との繋がりを再発見する、そういうことを丁寧に捉えていた」と受賞理由を話した。 準グランプリの『吟遊詩人 -声の饗宴-』について市岡は、「17分ワンカットで撮影されていて、そのカメラの力量に恐れ入った。カメラがちょっと動いたのは1ヶ所しかなくて、安定したカメラワーク。(エチオピアで弦楽器マシンコを弾き語るアズマリの、)日常的な批評精神の発露がよく捉えられていた。作者とエチオピアの人たちとの近さが感じられた」と感銘していた。 |
 |
『東京ドキュメンタリー映画祭』12月23(金)まで新宿K′s cinemaにて開催中 公式サイト: 公式ツイッター: 公式Facebook:
【映画祭事務局】 |
 EIGAJOHO.COM
EIGAJOHO.COM植山英美、大原博美、市岡康子、渡辺勝之、北村皆雄(下)佐藤寛朗、伊勢真一、鈴木一誌、竹岡寛俊、平野晃弘、林里穂、金子遊.jpg)